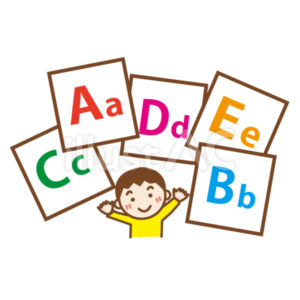行動観察について
2024年5月10日
近年の小学校受験では行動観察の分野に重点をおく小学校が増えています。
学校によってはペーパーテストの成績がトップクラスでも行動観察での得点が低く不合格になるケースもあるようです。
行動観察とは何でしょうか?
お子様が集団の中では、どのような振る舞いするのかを観察される試験です。
指示が理解できるか、社会性、コミュニケーション能力、協調性は身についているかどうか等をポイントに学校側の求める人材かどうかを判定されるわけです。
家の子どもは「ペーパーは得意だが行動観察が苦手」と言うご相談も多く頂きます。
専門塾もあるようですが一朝一夕に身につく力ではありません。
ご家庭の毎日の生活の中のいろいろな場面で、受験期前の幼少期から意識をもって、社会性、協調性、コミュニケーション能力を育んでゆけるよう心がけましょう。